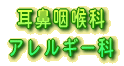<清水おかべクリニック>
<トップへ>
|
|
12月10日のNHK番組「ためしてガッテン」にて、蓄のう症(副鼻腔炎)の特集が放映されました。普段同疾患の治療に当たっている者として、マスメディアがどのようにこの疾患の事を伝えているのか興味があったので、視聴してみました。
以下にその番組内容の要約があります。
「蓄のう症予備軍1億人」とか、センセーショナルなサブタイトルが出てきます。
立体模型を用いて、副鼻腔と鼻腔との関係を示しつつ、副鼻腔炎という者がどのような病気なのかを目で見てわかりやすく示してくれていました。一般の方に受け入れやすい説明であったと思います。
ただ、ちょっと変だな、と思う内容もありました。
番組では「副鼻腔は8つある」と説明していましたが、違います。
上顎洞、篩骨洞、前頭洞の3種は、左右にそれぞれありますので6個。そして鼻の奥にさらに蝶形骨洞があるのですが、これは正中に1個あるのが普通です。ですから合計で7つ、というのが正解です。
でもまあ厳密に言うと、篩骨洞などはもともと多数の蜂巣から成り立っているのをまとめて一括りにして「篩骨洞」と呼んでいる訳ですから、数を数えあげる事にあまり意味はないのですが。
それから番組では、「鼻中隔が弯曲している人が、蓄のうになりやすい」というニュアンスの報道をしていました。確かにそういう側面はありますが、あくまで蓄のうの一側面にしか過ぎません。その事を理解していないと、とんでもない誤解を生みます。
番組の内容をそのまま捉えると、
1.鼻中隔が弯曲している人が蓄のうになりやすい
2.鼻中隔弯曲は子供で少なく(約5割)、大人で多い(約8割)
3.故に、大人ほど蓄のうになりやすい
という三段論法で、大人に蓄のう症が多いかのように受け取れてしまいます。
実際には、蓄のうは子供に圧倒的に多い病気です。免疫力が発達しておらず、始終鼻風邪を引いて鼻を垂らしている子供にこそ、蓄のう症は多いのです。そして時が経って成長し、だんだんに体が丈夫になり、鼻風邪を繰り返さなくなって蓄のう症の保有者が減る、というのが現実です。もちろん、大人でも鼻の粘膜がが弱くって蓄のうを繰り返す人はいますが、割合としては子供よりも遙かに少ないでしょう。
蓄のう症はまず子供に多い、アレルギー性鼻炎のある人に多い、そしてきつい鼻中隔弯曲のある人にも多い、と理解すべきです。
そういった説明が全くなされていなかったのは残念です。病気の説明に耳鼻科のドクターも出てきましたが、おそらく番組内容全体の監修はしていなかったのでは、と想像します。
他、蓄のうが酷いとCOPD(慢性閉塞性肺疾患)になりやすいとか、専門家から見ると「??」というような発言もありました。(COPDは喫煙者がなる病気)
NHKももうちょっと、きちんとした監修の元に番組を作ってほしいものです。
<診療日記に戻る>
|
|
|
|
|
 |
 |